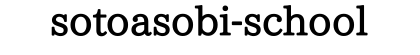昔は「木を見て、森を見ず」と言われて経験の浅い保育者は、目の前の子どものことは見るけれど、全体を見ることが出来ないと注意されたものです。
逆に経験者は、「森を見て、木を見ない」傾向にあるとも。
保育者は、木を見て、森を見ないと子どもの安全を守ることは出来ません。
全体を見るには、まずは全体を見るという意識が必要ですが、みんな「ちゃんと見てます。」と言います。
この「ちゃんと」を明らかにしないといけません。
必要な動作
全体を見るには必要な動作があります。
・顔を上げて、周囲を見渡す。
これだけです。
そのこれだけがなんと難しいことか。
それは、習慣化できていないからです。
動作としては至ってシンプルな動作でも、保育中に出来ているかというと甚だ疑問です。
それでは、この動作を習慣化するにはどうしたらいいか。
意識的に、ルックアップ、ルックアラウンドといった動作を行うのです。
最初は無駄に頭を上げてきょろきょろするだけでも構いません。
気が付いたら周囲を見渡すという動作を体で覚え、習慣化させるのです。
そうすると、無意識に周囲を見渡し、全体の様子を把握するくせがついてきます。
一流のサッカー選手は足元ばかりではなく顔を上げて、全体を把握しています。
私たちもルックアップ、ルックアラウンドを身に付けて、習慣化させましょう。
ポジショニング
次に保育者の立ち位置、ポジショニングです。
その場は全体を見渡せる場所か。
適切な位置もさることながら、どこを向くかということがとても重要です。
意識が全体を見ることに向いていれば、大勢の子どもに背中を見せるということは少なくなります。
全体を意識しながら適切な位置を探り、全体の中での自分の位置を確認し、どうポジショニングを取るか。
地味ながら保育者のセンスが問われます。
有効な無駄な動き
先生たちはちゃんと見ているんです。
もしかしたらそれが数m先かもしれません。
子どもは予想外の行動をすることがあります。
その時に、数m先では危険を回避するには間に合わない場合があります。
保育中、ベテランの先生の動きを見ていると、さりげなくすーっと動いて小さな声でささやいたり、危険を回避したりする様子がうかがえます。
あまり動いていないように見えて、じつにちゃんと動いているのです。
長年の保育経験から、子どもの行動を予測し、危険な場所にはあらかじめ近づいて何事もなかったように、危険を排除する。
予知能力の高い先生は実によく動きます。
子どもの行動特性から放っておいても怪我しなんてあるはずがありません。
実によく動き、有効なアプローチをしているから怪我を防ぐことが出来るのです。
こうしたポイントを押さえても事故を完璧に防ぐことは出来ません。
それは、保育というのは個人プレーではなく、チームプレーだからです。
チームとして機能していない現場は事故が絶えません。
しかしながら、個人の能力を高め、チーム力の高い保育現場は事故・怪我も少なく、活気にあふれています。
そんな保育現場を作るためのセオリーをお伝えし、子どもの事故・怪我が少しでも少なくなることを願っています。
森のようちえんの滝山ネイチャークラブ
代表 堀岡正昭