-
-
滝山ネイチャークラブ代表 さんが新しい記事を投稿しました。 2019年12月12日 8:46 AM
滝山ネイチャークラブは藤野の森のようちえん てってと平日の合同保育を行っています。
プレ森のようちえんの子どもたちが藤野[…]

-
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年12月5日 4:28 PM
人生においてもっとも大切なこと、
幸せになる方法や自分の心の守り方、落ち込んだ時に気持ちを切り替える方法、性のこと、家政学、その他ほとんど学校では教えてくれない。幼児期に出来ることがあるはず。
園でモノの捉え方や考え方、挑戦意欲や学習態度、人に対する信頼感など幼児期に学習することがふさわしい事柄をしっかり教えよう。
体験を通して自ら獲得し、学習できるように環境を整えるのが保育者の役目だ。 -
-
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年12月3日 5:49 PM
森のようちえんであれ、自然学校であれ、キャンプ団体であれ、個を大事にし、人格を尊重し、人間としての尊厳を守る団体・園・企業であるということが最も重要な基本的理念となる。
-
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年12月2日 5:34 PM
内面の変化は見えにくいとは言うけれど、実は表情、動き、言葉、遊びの様子、他の子との関わりから読み取れる。
プロはその微妙な差異に気づき、時にさり気なく、時に大胆に働きかけている。
写真は保育技術を高める。
どの一瞬を切り取るか。
どういった視点で見ているか。
1枚、1枚がその人の保育観が表れてくる。
子どものことがよく分からなかったら、子どもと距離を縮め、関わろう。
保育技術を高めたいと思ったら、とにかく写真を撮ってみよう。
振り返り、見返し、自分の保育を研ぎ澄まそう。 -
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年12月2日 5:13 PM
大人も子どもも成長したければ自分に負荷をかけよう。
子どもには、外部から大人が負荷をかけると大体、よくない。
子どもは、遊びの中では自ら負荷をかけている。
ちょっと難しい、ちょっと大変、丁度良い課題を知っている。
大人も自分に負荷をかけよう。
成長のための負荷をかけないと伸びない。
思っているだけでは成長出来ない。
行動して自分を変えよう。 -
-
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年11月26日 2:30 PM
働き方の制度や環境をいくら変えたって、自分自身が変わらないことには何も変わらない。
働き方改革の前に、自分自身改革、自己改革を! -
-
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年11月22日 7:51 PM
大切なものが見えにくく、分かりにくい時代になっている。
余計なことを考える余地がないくらい自然の中に身を委ねると、自ずと大切なことがよく分かるようになる。
子どもたちを自然の中に連れ出すのは、教育環境とか、教育効果ということもあるけれど、本当のところは、そうしないと大切なことを気づかせることが難しい世の中だからかもしれない。
街の中は、必要以上に人の眼が気になる。
本当に大切なことが曇ったり、自分を偽ったりしないと行き難い時代です。
そんな時代だからこそ、子どもを自然の中に連れ出そう。
大人も自然の中に勇気を持って一歩踏み出そう。
不自由さや不便さの先に、本当の自由が待っている。
お金で買えない本当の自由を獲得しよう。
本当に大切なことを自然の中で見つけよう。
-
-
-
滝山ネイチャークラブ代表 さんが新しい記事を投稿しました。 2019年11月17日 10:07 PM
「行きたくない」
そう言うことがあります。
親も先生も困ってしまい、どうしたらいいか分からなくなります。
東京学芸大学の心理学の大河原先生は、
「子どもが転んで泣いているのに、『痛くない、痛くない』とか『男の子なんだから泣かないの』なんて言ったりしませんか。」子どもは痛くて泣いているのに、外から「痛くない」と言われたり、「男の子なんだから泣かないの」と言われたりすると、感覚や感情に蓋をしてしま[…]
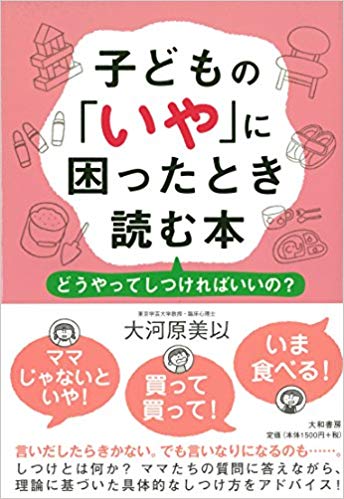
-
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年11月11日 10:46 PM
危険がないか、問題行動はしていないかを見るだけでは単なる監視です。
子どもの観察とは、内面の変化を読み取るのです。
それには共に過ごさないと見えてこないのです。
監視カメラにはこれが出来ません。
共に遊び、共に感じ、共に過ごすことでしか見えてこないのです。
逆に言えば、これを繰り返し訓練を積み重ねることで見えるようになります。
子どもをよく観察し、内面の変化を読み取る訓練を積み重ねることです。 -
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年11月11日 12:53 AM
指導計画よりも、子どもの観察と対応に力を入れよう。
怪我の心配をするならば、リスクを排除するだけでなく、怪我を回避する指導技術の向上に力を入れよう。 -
-
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年11月8日 11:23 PM
保育と言うのは、子どもと保護者、そして保育者を幸せにするものでなければならない。
滝山ネイチャークラブの森のようちえんは、子どもと保護者、そして我々スタッフの幸せに貢献することを目指します。 -
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年11月6日 8:55 AM
大切なことは毎日言ってもいい。
滝山ネイチャークラブは人権を守ることを求めます。
子どもの人権、自分自身の人権、みんなの人権。
人は自分がされたようにしか他人に出来ません。
それが当たり前のようになっていると人権を侵害したり、されたりしていることに鈍感になってしまいます。
(これは嫌いだな。食べたくないな。)
という気持ちを受け止めてもらえず、無理やり食べさせられてきた人は、子どもにも「あなたのためよ」と言って、子どもの気持ちを受け止めようとせず、無理やり食べさせようとします。
子どもには人権があり、あなたにも人権があります。
(嫌だな)という感情も表明してもいいのです。
「じゃあ、嫌いなものは全部食べなくてもいいんですね。」
それは違います。
ありのままを受け止めても…[ 続きを読む ] -
滝山ネイチャークラブ代表 が更新を投稿 2019年11月5日 5:21 PM
私たちはプログラムを詰め込みすぎることがあります。
プログラムを詰め込み、体験させることで、こちらの満足感、やった感が強いのです。
でも大事なのは、「子どもたちが獲得したもの」
プログラムで体験したことを全部忘れてしまった後に残ったものが、子どもたちが獲得したものです。・ゆとりある時間配分にしておくこと。
・大人の満足感より、子どもの充実感を大事にすること。
・この時の子どもが感じていることを共に感じ、見えないものの変化に敏感であること。そのためにすべての現場ですぐに出来ることは時間にゆとりを持たせること。
プログラムを詰め込み過ぎないこと。もちろんそれだけで終わったら「先生たちが楽をしたいだけ」になってしまいます。
何を子どもたちに獲得させたいのか理解…[ 続きを読む ] - さらに読み込む
代表「今日の一言」


 s-20191214 (43)
s-20191214 (43) s-20191117 (73)
s-20191117 (73) s-20191201 (16)
s-20191201 (16)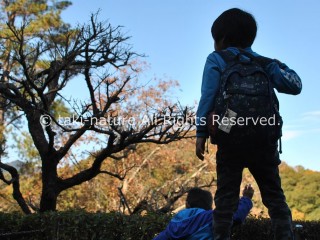 s-20191201 (18)
s-20191201 (18) s-20191116 (16)
s-20191116 (16) s-20191116 (42)
s-20191116 (42) s-201911お泊りキャンプ (199)
s-201911お泊りキャンプ (199) s-201911お泊りキャンプ (93)
s-201911お泊りキャンプ (93) s-DSC_3390
s-DSC_3390 22885…
22885… s-20160522-152
s-20160522-152 s-20191117 (75)
s-20191117 (75) s-20191109 (104)
s-20191109 (104) s-20191109 (130)
s-20191109 (130) s-20191109 (29)
s-20191109 (29) s-20191103 (9)
s-20191103 (9)